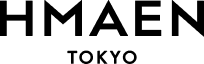藤巻幸大が各界で活躍する方々をゲストに招き、“モノとのつきあいかた”を語り合う「ゲストインタビュー」。今回のゲストは世界的なシェフであり、五大陸に31店舗もの日本食レストランを展開する希有なレストラン経営者でもある、松久信幸さん。虎ノ門にある「ノブ・トーキョー」でお話を伺いました。(後編)
前編はこちら

すべてを失ったアラスカの夜。
支えてくれたのは家族でした
藤巻 ノブさんがアラスカで経験された、ある挫折とはどのようなものだったんですか。
松久 オープン直後の感謝祭の夜、店が火事で全焼。すべてを失ってしまったんです。パートナーに「すぐ来い」と電話をもらい、駆けつけたときには店は炎に包まれていました。
藤巻 ……。
松久 それから一週間ぐらい、記憶がすっぽり抜け落ちてしまっています。何も食べられず、水を飲んでも吐いてしまう。死ぬことばかりを考えていました。でも、あまりにも打ちのめされてしまって、死ぬ気力もない(笑)
藤巻 凄絶な経験をされたんですね……。
松久 僕があの時、死なずに済んだのは、女房や娘がそばにいてくれたおかげかもしれません。無意識のうちに彼女たちの笑い声が耳に入ってきたからだと思うんですが、ある瞬間、もう一回やってみようと思えた。
藤巻 その決意はこれまでのものとはまったく違っていましたか。
松久 そうですね。焦りがなくなったような気がします。それまでは「友達も頑張っているんだから、俺も!」のような気持ちもあった。でも、今は、こうしてチャンスを与えられたんだから、1日に1ミリでもいいから前に進もうと思う。
藤巻 まさか、そんな壮絶な経験をされていたとは……。
松久 あの頃のことを思い出すと、今でも涙が出てくることがあります。その後、心機一転、単身で米国に渡るんですが、家族に会いたくて、会いたくて……。当時働いていた町にはすぐ目の前に海があって、少しでも家族の近くに行きたくて、一歩二歩海に入るような時期もありました。
藤巻 そうした想いや経験をすべてひっくるめて、今の“世界のノブ”があるわけですね。
松久 あの頃、家族がいなければ、ヤケを起こして簡単に逝ってしまったかもしれないし、自分の不運を呪い続けていたかもしれない。家族の支えがあって、どうにかそこを脱することができた今、僕にできることはただ、一生懸命生きていくことだと思えるようにもなりました。
稀代のシェフが最も安心し美味しく感じられる料理とは――
藤巻 ノブさんにとって「手放せないモノ」って、どんなモノですか。
松久 そうですね……。じつは僕はモノにはあまり執着がないんですよ。「なくなった」というほうが正しいのかな。今まさに、引っ越しのためにあれやこれやと処分をしている真っ最中。想い出が詰まったものを捨てるのはしのびないことではあるんだけれど、後生大事にとっておいても、将来、僕や女房が死んだときに子どもたちが大変な思いをするだけだなあと。

藤巻 うちの親父は13値年前になくなったんですが、最後に残されていたのは引き出しにネクタイ二本と背広が二着、それから東芝の社員バッジ。「これだけは捨てないでくれ」というのが親父の遺言でした。仕事を愛し、必死に働き、家族を養ってくれた。じつに親父らしくて、家族みんなで泣きました。
松久 車や時計といったものに執着心の薄い僕にもどうしても捨てられないものがありました! 女房と家族(笑)。
藤巻 ははは。確かに! 家族の存在というのは大きな支えになりますよね。
松久 一年間のうち大半は自宅にいないし、ロスアンゼルスにある自宅に戻っている時期も昼や夜や店に出て、スタッフが作った料理を食べます。でも、朝は女房が作った食事をとる。じつは女房が作る朝食が、僕にとって最も安心して、美味しく感じられる料理なんです。
藤巻 それは素晴らしいことですね。
松久 海外での生活が長いけれど、僕はやはり、米飯にお新香や味噌汁、塩鮭、納豆といった、和食が大好き。さぞかし贅沢なものをたくさん食べてきたんでしょうと言われるけれど、じつは一番惹かれるのは幼い頃から慣れ親しんできた、お袋の味なんですよね。
藤巻 いい話ですねえ。

人生を伝え、後進を
育てるという、新たな使命
藤巻 30年以上に渡って「食」の最前線をひた走りに走ってこられたノブさんの目に、日本の食シーンはどう映るのか、ぜひ伺いたいです。
松久 食に関して言えば、日本は世界に類を見ない先進国ですよ。多種多様なジャンルの食があり、食に対して興味関心を持っている人も大勢いる。新鮮な食材が、こんなにもふんだんに手に入る国は世界中探しても、そうそうありません。世界一と言ってもいい。ただ、課題をあげるとすれば、ハングリー精神。何でもあるからこそ、工夫に対する熱意が乏しい側面もあります。
藤巻 何も手を加えなくても、美味しいものが食べられてしまうことで、結果、クリエイティビティが発達しづらいのでしょうか……?
松久 現在のフレンチスタイルもそうですが、あれこれ手を加えるよりも、できるだけシンプルに素材の美味しさを活かすという考え方は決して間違っていない。でも、素材のポテンシャルに頼り切るのではなく、もっともっと感銘を受けられる“何か”があるはずだとも思うんです。魚の切り方ひとつ、寿司の握り方ひとつとってみても、そのシェフにしか作れないものがある。

藤巻 『NOBUのすし』を始めとする、ノブさんのレシピ本を見れば、ノブ流をマネすることはできるかもしれないけれど、当然ながら同じものは作れない。
松久 同じようにできなくてもいいと思うんですよ。むしろ、僕のレシピを参考に、自分流を作ってくれればいい。実際のところ、海外のレストランで、おそらく元ネタは僕のものであろう料理に出会うことがあり、すごく嬉しく、幸せな気持ちになる。僕が生み出したものが沢山の人に支持され、広がっていった証ですから。
藤巻 最後に、これからのノブさんがやってみたいことを教えてください。
松久 自分がやってきたことや考えをまとめて、次の世代に伝えていくことでしょうか。我々職人はよく作品を作るのはもちろん、その技術や志を教えることができて一人前だと思うんです。
<対談を終えて……藤巻幸大から松久信幸さんへ>
覚悟を決めた人はとてつもなく強い。
ノブさんの笑顔の向こう側に、あんなにも凄絶な過去があったとは思ってもみませんでした。
僕自身、心臓と目を患い、死の淵から舞い戻って来ちゃうという経験をしていて、
そのときに、生きる姿勢がガラリと変わったという体験がある。それだけに、ノブさんの言葉ひとつひとつが沁みました。
ノブさんは根っからの職人であり、世界中で展開されるレストラン・ノブの経営者であり、多くのスタッフの親父でもある。
こんなに素晴らしい大先輩と、同じ時代に生きられることを誇りに思います。
今夏に刊行させるという、ノブさんの人生の集大成である書籍も楽しみにしています。
-
-

-
【NOBU】「NOBU×藤巻百貨店 オリジナルワイングラスセット」
世界の食通を魅了するNOBUフードが生んだ、驚異の耐久性を誇るワイングラス
7,370円(税込)
-
松久信幸
まつひさ・のぶゆき●1949年埼玉県生まれ。小学1年生の時に父親を交通事故で亡くす。高校卒業後、東京の寿司屋・松栄で7年間修業をした後、24歳でペルーに渡り、パートナーで寿司屋を経営する。その後、ブエノスアイレス、アラスカを経て、87年にロスアンゼルスに「MATSUHISA」を開店する。94年にはニューヨークに「NOBU」をオープン。以来、ロンドン、ミラノ、ギリシャなど各国に次々とレストランを展開。














 もっと
もっと