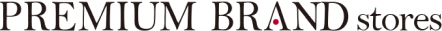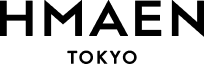竹や萩などの天然素材と木綿糸で編み上げられる素朴な「江戸すだれ」。語りすぎないその凛とした佇まいのなかに宿る、日本人の暮らしぶり。本物の簾づくりを貫く田中製簾所の5代目が、細部にまで技を尽くしたランチョンマットとコースターは、ひと味違う。 商品詳細はこちら

万葉の時代から暮らしの傍らで
目隠しとなり、風通しとなり
窓辺に垂らせば、陽射しや人目をほどよく遮り、風や光はやさしく通す。簾は、古代から現代に至るまで、その形や用途を変えることなく使い継がれてきた、日本人の暮らしに欠かせない道具のひとつ。万葉集をはじめ、数多くの書物にも記述が残されている。なかでも『源氏物語』の、柏木が女三宮を垣間みる名場面。猫が開けてしまう一枚の御簾(みす)は印象的だ。簾には、内と外との境をやんわりと引きながら生きる日本人らしさが漂っている。簾づくりの本場は京都だが、徳川の世となり、江戸の町にも腕利きの職人が増えていく。江戸中期、元禄年間発行の当時の職業絵本『人倫訓蒙図彙(じんりんきんもうずい)』にも“御簾編(みすあみ)”の姿が見える。この仕事ぶりを今に受け継ぐのが、伝統工芸「江戸簾」だ。

「投げ玉」の音が響く工房で
青竹は手塩にかけられ簾になる
簾づくりはまるで機織りのよう。重し、兼、糸巻き役の「投げ玉」を木綿の糸の両端に括り付け、わずか5.5mm幅の編み台を挟み、前後へ行き交わしながら、竹ひごを1段ずつ編んでいく。リズムよく飛び交う投げ玉が、工房に高らかな音を響かせる。簾づくりならではの光景だ。簾の材料は竹が一般的で、工房に届いた青竹は、まず一定の長さに切られ、籾ぬかや砂、塩を使って洗い、ふしを削る「下ごしらえ」が施される。その後、「割り」や「へぎ(厚みをそいでいく作業)」で形が整えられ、7~10日間の「天日干し」を経て、ようやく「編み」を迎える。そして、編み上がると両端を大ばさみで切り、上下に桟(さん)をつけて完成となる。こうした「江戸簾」の技を受け継ぐ伝統工芸士は、たったの2人。浅草、田中製簾所の親子が担う。

昔も今もオーダーメイドの心意気
いい素材あっての本物の簾
田中製簾所は明治初期の創業。「昔から使い手は生活者。家の環境により要望は多様で、それに応えるには“一目的一道具”。道具から手作りです」と先代の義弘さん。簾の素材や糸によって重さ・大きさをかえる投げ玉が、数えきれないほどあることにも納得だ。5代目、耕太朗さんの元には、100年以上前に作られた簾の修理も舞い込む。「バラしてはじめてわかる編み方もあり奥深いです。驚かされるのは昔の素材の良さ。簾は天然ものだから、どれだけちゃんとした素材で作れるかが大事」。竹は専門の竹屋から身の硬い冬場の青竹を、高級素材の萩や蒲などは信頼できる農家から直接仕入れている。しかし、素材の調達は年々困難を増しているという。「いい素材のつくり手がいるから、本物の簾づくりができています」。

凛とした美しさをテーブルへ
大胆なマリアージュを楽しみたい
田中製簾所はもともと建具用の簾を専門としていた。建物の一部に建て付けられるとなると、仕上がりは寸分違わぬものでないと納まらない。そのため、縫い糸の幅取りも緻密で、そのつど編み台のスケールを替えながら作業は進み、端の処理など細部にも目が光る。結果、美しさが違う。それは「ランチョンマット」や「コースター」になっても変わらない。簾のテーブルウェアは、今や目新しいものではないかもしれない。しかし、本物の簾のテーブルウェアは、なかなかない。食べることが好きで、すでに皿や酒器やカトラリーはお気に入りがあるけれど、少し異なる装いがほしい。そんなテーブルにぜひ加えてみてほしい。竹素材は本来、季節を問わず使えるもの。季節にも、和食にもとらわれず、ぜひ、大胆な楽しみ方を。
お取り扱いアイテム
-
-
 品切
品切
-
ランチョンマット
東京都伝統工芸「江戸簾」で作るランチョンマット
【田中製簾所】ランチョンマット4,400円(税込)
-
-
-
 品切
品切
-
コースター
東京都伝統工芸「江戸簾」で作るコースター
【田中製簾所】コースター550円(税込)
-













 もっと
もっと