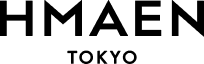天然の山羊や馬の毛を、ひと穴ひと穴、手で植え揃えていく「東京手植ブラシ」。刷毛づくりの技を活かしてつくり継がれる宇野刷毛ブラシ製作所のブラシたちは、まさに正統派。時代を越えたスタンダードが、肌をやさしく洗う。 商品詳細はこちら

日本の伝統的な刷毛づくりの技が
ブラシづくりに受け継がれた
ブラシは漢字で「刷子」と書く。日本でブラシが作られるようになった明治初期、刷毛(はけ)職人たちが製造を担ったことに由来する。刷毛とブラシの違いは、刷毛は主に“塗る”道具であり、ブラシは“払う”要素が強いといえるだろう。1870年代、フランス製のブラシを手本に製造がはじまった日本のブラシ。当初は「洋式刷毛」とも称された。産業機械が普及するとともに工業用にブラシが使われるようになり、同様に一般家庭でも生活の欧米化が進み家庭用ブラシの需要が増していったこの時代。世の中はブラシの大量生産へ向かっていったが、その一方、東京では職人の手植えによる耐久性の高いブラシも作られていた。それが現在の伝統工芸「東京手植ブラシ」につながる。1917年、大正時代創業の宇野刷毛ブラシ製作所も、刷毛づくりの技を活かし、手植えのブラシを手がけるようになった一軒だ。

“つぼ錐(ぎり)”で開ける穴の形状が
丈夫さと毛先の表情の秘密
手植ブラシは、“木地(きじ)”と“ステンレスワイヤー”と“天然毛”から作られる。引き線と呼ばれるステンレスワイヤーを二つ折りにして穴に通し、そこに毛を通して穴に植え込んでいく。ひと穴ごとに毛が植え込まれる機械植えと違い、ステンレス線でつながっている手植えは毛が抜けにくく丈夫なのだ。木地に穴を開けるのも手作業で、“つぼ錐(ぎり)”と呼ばれる道具を使う。“つぼ錐”を使うことで木の正面(毛の出る側)と背面に数ミリの穴の差が生まれ、背面の穴の狭さのおかげで毛元がしっかり植わるとともに、正面に向かって穴が広がることで毛先がほどよく開くのだという。また、穴の大きさや間隔も、ブラシの用途や合わせる毛によって異なり、工房にはブラシの設計図ともいえる穴開けのパターンが数多く保管されている。

手で毛量を見極め
流れるように植えていく職人技
ブラシの主役である毛の世界も、奥深い。動物の天然毛が使われるのだが、山羊の毛はフェイスブラシ、馬の毛はボディブラシ、豚の毛はつめブラシ、猪の毛はヘアブラシなどへと、その特性に合わせて使い分けられる。馬の毛はさらに、尾の毛、胴の毛、たてがみの毛、足の毛に大別され、尾の毛のなかでも、太くて長いものは“本毛(ほんけ)”と呼ばれる。柔軟性と弾力性に富む本毛をしっかりと混ぜ合わせ、ブラシの硬さを均一にするのだという。製作所の3代目、宇野三千代さんは、握り具合で毛量を計りながら、流れるような手さばきで植えていく。「最も扱いにくいのは、剛毛な猪の毛。引き込むのに、かなりの力が要ります」。繊細な感覚と力、両方が必要な仕事なのだ。

細部への心配りが生む機能美
浴室の風景を変える1本
それぞれの毛の特性を知り尽くし、確かな技術で手植えすることはもちろん、その使い心地の良さ、無駄のない美しいブラシに仕立てあげるのが宇野刷毛ブラシ製作所の真骨頂だ。素肌に使う身体用のブラシは、ひときわ丁寧にすべてのカドが落とされ、露出したワイヤーが体に当たらないように木でふたをし、そのふたを留める釘の頭も丁寧に丸く処理されている。この真鍮の小さな釘がまた、いい味を出している。「手で仕事をするという原点を大切にしながら、常に進化させる。そうして仕事をしていると“伝統”という言葉は後からついてきます」と、2代目の千榮子さん。ブラシが仕上がると、最後に「言問橋 宇野 東京」の焼き印が打たれる。隅田川のほとり、言問橋の傍らの小さな工房から送りだされる1本のブラシが、毎日のバスタイムを待ち遠しくさせる。
お取り扱いアイテム
-
-
 品切
品切
-
洗顔ブラシ
伝統工芸「東京手植えブラシ」で作る、柔らかな洗顔ブラシ
【宇野刷毛ブラシ製作所】フェイスブラシ3,300円(税込)
-
-
-

-
ボディブラシ
伝統工芸「東京手植えブラシ」で作る、体洗い用ブラシ
【宇野刷毛ブラシ製作所】ボディブラシ/長柄7,150円(税込)
-
-
-

-
ボディブラシ
伝統工芸「東京手植えブラシ」のボディブラシ。中柄で扱いやすい
【宇野刷毛ブラシ製作所】ボディブラシ/中柄6,600円(税込)
-













 もっと
もっと